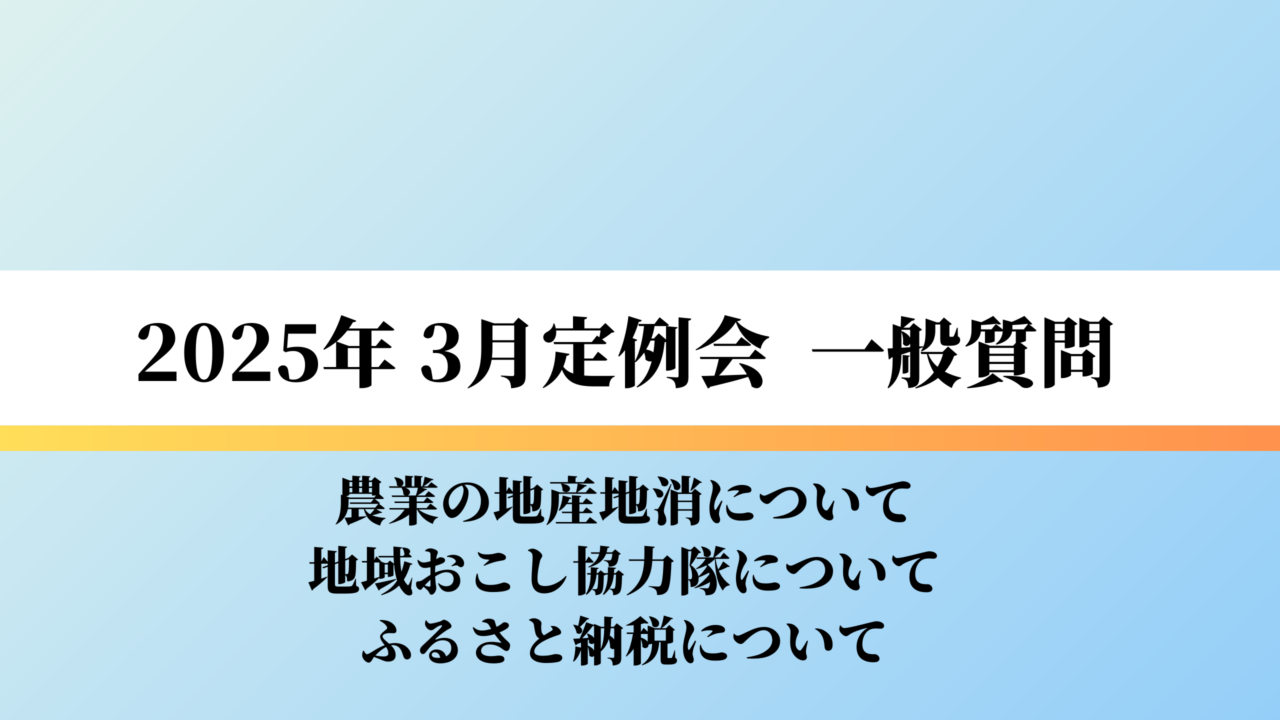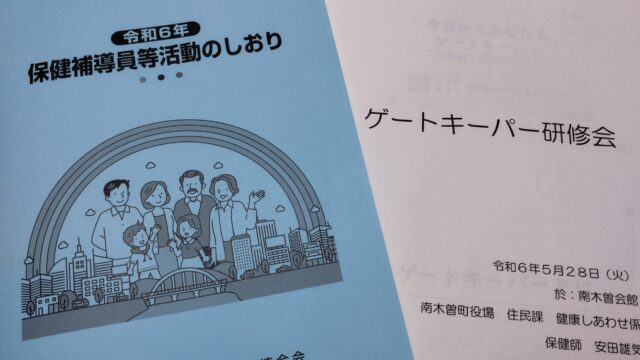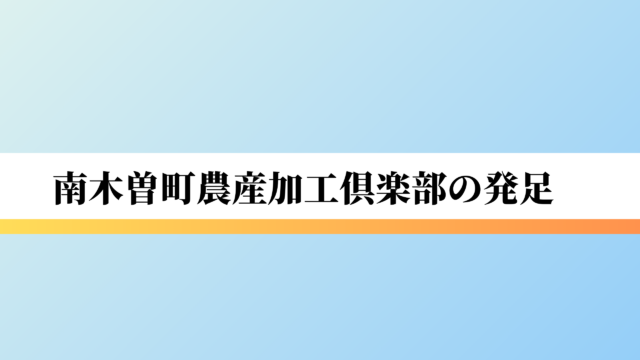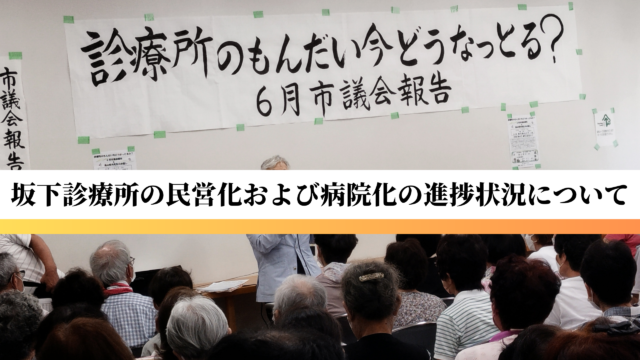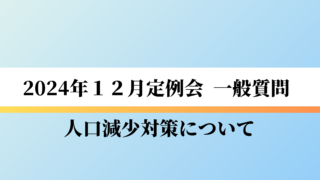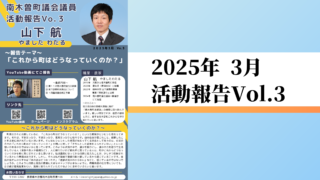2025年3月定例会の字お越しになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1番山下議員一番山下です通告に基づいて、一般質問を行いたいと思います私は、農業の地産地消の推進について地域おこし協力隊について、ふるさと納税について質問いたします。
詳細につきましては自席で行いたいと思います。
一番山下議員はい。
一番山下です。
よろしくお願いします。
まず農業の地産地消の推進についてお願いしたいと思います。
地産地消の推進推進について総合計画案の中でもこれまで示されてきました。
今回の第11次南木曽町総合計画案には、第10次総合計画に加えて農産加工場の開設の検討案も盛り込んでいただきました。
私としましてはこの計画が実現されれば町の重要な施設になるのは間違いなく、地産地消の推進に大きく貢献し、てくれることと思ってます。
そこで質問なのですが、現在の南木曽町の地産地消の取り組みと今後の取り組みについてお伺いしたいと思います。
【町長】
町長はい。
人口減少対策を進めることで地域を維持していくとともに、地域経済も維持できるようにしていかなくてはなりません。
地域経済を活性化する上では、地産地消の取り組みといったものが欠かせないものの一つになろうかと思います。
これまでも地元農産物の学校給食への活用、小中学校の机と椅子の製作あるいは町並み交流センターのように、地元産材を地元業者が製材して、地元の大工さんが関わって作ったり、さらには地域商品券のように地域で
消費を増やす事業を行ってきているところであります。
小さな町の経済を活性化していくためには、地産地消の視点も大切にしながら、地域経済が回る仕組みを作っていくことが大切だと考えています。
行政のみならず、事業者や住民といった地域全体で同様の考え方が持てるように、意見や提案などをいただきながら、仕組み作りを行っていきたいと考えているところでございます。
ご質問の際に、具体的な内容につきましては、産業観光課長からお答えをさせていただきます。
産業観光課長
産業観光課長です。
南木曽町地産地消協議会では、軽トラ1部会と学校給食部会が活動を行っています。
軽トラ第1部会では、毎年6月から12月まで、おおむね月1回駅前広場やJA木曽南木曽金融店で、軽トラ市場南木曽グリーンマーケットを開催しています。
また、野菜の自動販売機を令和4年度に導入し、現在は南木曽駅前広場、天白公園および南木曽会館に設置して、野菜の無人無人販売を行っております。
学校給食部会では、小中学校の給食地元野菜の提供を行い、町は部会員が学校まで野菜を運搬し、する費用に対して補助を行っております。
また、学校給食の主食用米は地元米を販売購入をしております。
また、南木曽ウェルネス農泊協議会では、地域の食材を活用し、提供を行う取り組みを行っておりますので、その活動に支援を行っております。
地産地消の視点を大切にしながら、地域の生産や消費を増やす取り組みを考えていきたいと思っております。
山下
一番山下議員、一番山下です。
では今後の取り組みっていうのはそれを継続させていくということでよろしいでしょうか?
観業観光課長
はい。
継続して取り組んでまいります。
山下
一番山下議員一番山下です。総合計画案に常設直売所農産加工場の開設を検討するという部分がありますが、また令和5年度評価した地方創生総合戦略の政策評価の報告書にはこう書かれてます。
庁内に加工場の建設を希望する声もあるが、運営主体、自主財源、規模等、課題は多く、検討はするが事業化はまだ先と考える当面は現在活動している団体を支援し、加工食品を推進していくとあります。
総合戦略には、案にしては加工場や常設直売所開設の検討ということが書かれてあるんですけどもこれまでも総合戦略は見直しがあってちょっとずつ変わっている現状があって、懸念している部分があります。今のこのお考えなのかどうかをお聞きしたいと思います。
産業観光課長
はい、産業観光課長です。
はい。今ある団体を支援していくということでお願いします。
加工場にことにつきましては、加工場を運営していく団体、あと金銭的な問題もございますので、現在も研究していくっていう段階でございますのでお願いします。
山下
一番山下議員はい一番です。
すぐに具体的に、現時点で明確にはできないとは思いますけども、私としましてはぜひとも進めていただきたい計画であります。それで直売所が工場に関しては、それぞれ全国で2万店舗以上あって、売上高や売り場面積、運営主体のデータなどはあります。生産者の所得が向上した雇用が創出されたなど効果も出ています。合わせて2兆円以上の市場規模でもあります。
この政策なんですけども加工時や直売所を作るという政策の趣旨ですが農家自体が元々農林畜産加工所というハードだった。
のにそれが使えなくなったから、代わりのハードを作ってですね、機能を取り戻すという趣旨だと思います。
拠点施設を作ったところの生産者の所得が向上したのはまだその農家の技術がそこには生きていたからかなというふうには思っております。
これは意見ですので、情報として伝えさせてもらう部分なんですが、今回また大きな理由としましては、この街全体の活性化住民の消費を町外へ流出させないという大きな利点があります。
直近で出してもらった令和6年のデータによりますと、事業収入など加えず、9給与収入、年金収入のみで計算した、南木曽町民の全世帯の年収を合わせた額が約91億円になります。
そして令和2年、4年前の同じく、南木曽町民の全世帯の合計年収は98億5000万円ありますから4年で約7万5000円、7億5000万円の減です。人口減少によってかなり町民の消費力が落ち込んでいることがわかってきました。
この全世帯の約91億円の収入を1650世帯で割ると、世帯当たり平均年収が約550万円になります。この平均年収も令和2年映画約570万円ありますから、4年間で約20万円の減です。
おそらくですが人口減でどんどん総年収は下がっていきます。待ったなしの状況です。
南木曽町の経済を活性化するためにはこの総年収のうち、どれだけ町民の皆さんがこの南木曽で消費してくれるかによって大きく影響してきます。
今回は地産地消ですので、食費の部分に当たるわけですが、その食費が中山間地だと1世帯当たり約50万円が使われていると言われています。
地産地消の目的を果たすならば、この50万円を全て南木曽町で消費してくれるのが理想だと思います。
しかし現実は町外で野菜や加工食品、生協などで購入している方々が多いと思います。
また通信販売、ネット販売が出てきたことで流通を凌駕して物を購入できるようになり、地方の消費はかなり流出していると予測できます。
現在南木曽町では町外で消費をしている方が多いと思われますので、まだ南木曽町には地産地消の効果によって活性化できる可能性が十分あります。こういった町外で流通している消費を常設直売所、農産加工所、そういった施設があることによって止めることができますし、これは意図的に戦略的に流出しないようにしないといけません。
南木曽町だと1650世帯×50万円なので約8億円以上の売り上げをどれだけ止めることができるかということになってきます。
この南木曽の経済の活性化に繋げることができる直売所や農産加工所がその役割を担える施設であると考えられますし、これは農業だけに限った話ではありません。
今南木曽町がスーパーの閉店などの話が出てきているので、この街の中の全体の位置づけとして非常に重要だということをお伝えさせていただきました。
最後に一点なんですが、これはもし開設に向けて話が進んでいく場合のことになりますが、南木曽町はやはりそういった施設の場所の問題があると思います。
家の中に家事動線があるように、住民の1人1人の生活動線というものがあります。ある方は、家の近くのバス停でバスに乗って、南木曽駅で降りて病院で診察を受ける。そして帰りにスーパーに寄って、その後駅の待合室でバッチバスを持って、待って帰る。スーパーで買った品物はスーパーのサービスで夕方に家まで届けてくれると高校生であれば帰りに駅前に来てスーパーによる子たちもいます。
観光客の導線もあります。このように時間帯は違えどあらゆる属性を持った人たちの生活動線が重なる場所があります。
それはこども園であったり、飲食店であったり、郵便局であったりスーパーであったり、施設を軸にして住民の人たちが動きます。
以前から住みよい街というはどういうものかと問われているとは思うんですが、住みよい街のそういったグランドデザインがイメージできてないと施設がてんでバラバラの配置になるんじゃないかと懸念しています。町民の暮らしに注目をして、町の経済公開のことも考えてぜひとも解説について議論を1個進めていけたらなと進めていただけたらなというふうに思います。
今回はこれは意見としてお伝えさせていただきますので地産地消の質問については以上となります。
地域おこし協力隊について
それでは次に地域おこし協力隊について質問させていただきます。
地域おこし協力隊の隊員数は令和5年度には全国で約7200人が活動しており、総務省は令和8年度までに1万人にするという名目標を掲げています。
この制度は特別交付税措置がとられているということですので、これからもこの制度をうまく活用していただきたいと思います。
そこで地域おこし協力隊制度の取り組みについて質問したいと思います。
手順に繋がっている協力隊の人数は、どれぐらいあるでしょうか教えてください。
戦略室長
はい戦略室長です。
地域おこし協力隊制度は2009年に創設され、都市部から過疎地域に移住し、最長3年間、地域に居住し、地域振興活動などを行いながら、任期終了後、起業就業定住を図る取り組みで、南木曽町については2014年度平成26年度からですね、導入をしております。
令和6年度は導入から12年を迎え、これまでに11期、24名の方を採用し、現在は現在では5名が活用活動している状態でございます。なので今の時点で19名の方が退任したというような形になります。
退任した19名のうち、任期3年間を満了した方が13名います。
中東退任した方もいらっしゃいますので、その13名のうち、現在も町に定住している方は、6名となります。
また現隊員の中で、この3月をもって2人がお2人の方が任期満了で退任します。1名が研修先に就職1名につき1名につきましては、転出となるような形になっております。
山下
一番山下議員、一番山下です。
長野県の地域おこし協力隊の定住率は大体60%から70%だと思うんですけども協力隊の人数でも全国で北海道に次いで2番目に多く、長野県なのでそれを考えると少し定住率は低いのかなっていうふうには思えるんですが、とはいえまだ11機ぐらいだと思いますし、南木曽町でこの制度の活用の仕方等を考える上で、まだまだ母数が少ないように思います。そこは考慮できる部分なのかなというふうに思います。
なので、隊員として活動を終えた後、一定数は南木曽町に残ってくれているということですから、数だけの理論で言えば、どんどん採用した方が単純に定住してくれますし任期終了後に事業などを起こしてくれれば雇用も生まれていいのかなとは思うんですが、そこで次の質問なんですけども採用人数について制度的なことや、南木曽町で採用できる許容人数の制限等はあるのかどうか伺います。
戦略室長
戦略室長です制度的に採用人数についての制限等はないというふうになっております。
うちでは、実施計画で毎年2人の方を採用するというような形で計画をしています。
その年の募集条件や応募状況等に応じて若干の人数の差が生じておりますが計画的には毎年2名というような形で計画をしております。
協力隊についてはそれぞれ目標や目的を持って着任していただいており、それぞれの活動を戦略室の担当がサポートしていることからも、それほど多くの人数の方を採用するということはちょっと現実的にできませんので毎年現在の2名ずつという人数が適当だということで現在判断をしているところでございます。
山下
一番山下議員。
はい、違いますです。
ということは、2名以上の採用人数以上にたくさん応募があって、人物的なこと南木曽町でやろうと思っていること、そういったことに問題がなければ、採用はできる条件がいる人がいるにも関わらず2名しか採用しないっていうこともこれまであったということですかね。
はい戦略室長はい戦略室長です逆にというか、現在2名といういうような形でやっておりますが条件等があって、2名以上採用したこともございます。
山下
一番山下議員。
はい。
一番山下です。
ありがとうございました。チャレンジ中のプロジェクトでマッチングした。ジェクトワンさんとネクストCommons Labさんも事業を展開している新潟県三条市なんですけども40人ぐらい地域おこし協力隊が活動しているみたいです市なので、規模が全然違いますが、地域おこし協力隊が大勢いると、これから地域おこし協力隊になろうとする人たちも応募しやすい雰囲気が作れるのではないかなといった理由で質問をさせていただきましたということでこの件について了解いたしました。
次の質問ですが、こちらは住民の方たちも、以前から要望があった。
あるものですが、南木曽町はもっとPRしてほしいと私も南木曽のことをもっと発信できると思っています。ホームページを改良していただけるということで、それでこれからもし今後YouTube動画やSNSでの発信を活発にしようとしたら結構な時間が取られると思います。
そういったことでやはりある程度、動画編集などができる、できるレベルのPR人材が必要かなと思っています。
そこでPR専門の地域おこし協力隊を募集してみてはどうかと思いますが、いかがでしょうか?
戦略室長
はい戦略室長です。
現在今年4月採用予定の協力隊は、ミッション型として現在整備している移住体験住宅の管理運営および移住コーディネーターとしてのとしての活動として募集し、1名採用を予定しています。
この隊員には、移住体験住宅の管理運営だけでなく、町の宮魅力をPRし移住希望者を募る活動や、最近体験住宅利用向けの町内以上通話などを担っていただくことも期待しており、町のPR活動についてもご協力いただきたいいくようになっております。
山下
一番山下議員はい。
一番山下です。
この質問したのは、やっぱり専門じゃないと厳しいのかなっていう私の考えがありまして、やっぱり情報を発信しながら何かやるってのはかなりの時間を要するものなので、南木曽町を思いっきりPRしていくっていうことにはなかなか繋がらないかなというふうに思っています。
多くの地方自治体がもう既にたくさんPRしてますし、そのPR合戦の中で多くの人に、南木曽町を認知してもらわなければならない状況です。
そして大事なことなんですけど
魅力っていうのは作るものだというふうに私は思っていまして、例えば最近YouTubeの動画なので、犬猫を紹介した動画がありますが、すごくかわいいので再生数も多いです。
ただ、もちろん中には犬猫が嫌いな人もいます。そういった人は動画を見ないと思いますが大事なことはこの犬猫は何も変わらないということです。
犬猫が好きという人と嫌いという人がいて、好きな人が動画を作って発信して、いろんな元々好きな人がその動画を発見して見ているという状態です。
この町も一緒で、南木曽はもう何もないっていう人もいますし南木曽のここが魅力だと思ってる人もいます。
魅力があるないという人がいるだけであって、南木曽町自体は急に何か変わるものではありません。ただ言ってるのっていうだけで何も伝わらないので、写真や動画を作って、元々山の景色や映像時代の町並みなどが好きな人のところにネットなどを使って発信する。
元々基礎のような場所が好きな人のところに情報を届けるだけなんですねそれをどれだけやれるのかっていうことがこの南木曽町の認知度に大きく影響してきます。専門的にやられて今の状況では厳しいかなというふうに提案をしておきたいと思います。
また地域おこし協力隊でなくても、デジタル庁ができましたこれからのデジタル社会において情報をきちんと扱える人材、人員が必要ではないかと思います。
また今、広告プロモーション漁業だけでビジネスが成り立つ世の中ですので、またホームページの改良をしていくことで、ですのでこのページを改良していくという事なのでこれからちょうどいいタイミングではないかと思いましたできれば検討していただきたいと思いますので、要望ということでお願いしたいと思います。
以上これ以上はい。
お願いします。
はい。
次にふるさと納税について質問したいと思います。
南木曽町のホームページからの情報ですが、平成26年から寄附金額や寄付金の使い道が公表されています当初よりも、返礼品の数も140を超えて増えてきており、リピートして寄付をしてくれている方々もいます。
かなり大きな財源となってきてますので今後の取り組みにも期待したいと思っています。そこで質問ですが、寄付金が増加してきた要因と今後の取り組みについて教えてください。
戦略室長
南木曽町のふるさと納税は、平成26年から始め、平成29年からは業務の一部を事業者、須佐と古山へ委託し、返礼品をホームページで紹介し、寄付を受け付けてきたところでございます。
また、令和4年からは楽天とも契約し、多くの皆さんの目に留まるようにしてきました。
民間事業者が窓口となることで広く目に留まったことと、事業者事業者の負担となっていた返礼品の登録事務をし、事務について商工会に担っている
いただき、返礼品の登録数を増やしたことも、寄付増加の大きな要因だったと考えられます。それで今後の取り組みとしましては、以前に他の議員からも提案がありました。
返礼品なしのふるさと納税、長野県では「がちなが」という名前で実施していますが、当町においても、この先ほど紹介したさとふるのシステムを使って実施できることができるということで確認をしております。
また令和7年度からは、クラウドファンディングによる寄付の受け付けも行います。
通常のクラウドファンディングでは、目標金額まで達しないと寄付の受領が成立しないということですが、この佐藤ふるさと納税で使ったシステムにおいては、目標金額以下でも受領することができるので、そちらの方でやっていきたいと考えております。
この4月1日から耕作放棄地を解消した市地域活性化を図るエゴマプロジェクトということでやっていきたいと考えております。
この他、南木曽町の特産品や伝統工芸品をさらに多くの皆さんに見ていただけるよう、さらに窓口の拡大を検討していきます。また、同時進行で新規事業者の登録や、既存事業者による新規の返礼品の登録を引き続き進めていきたいと考えているところでございます。
山下
一番山下議員はい。
一番山下です。
今後の取り組みについては大賛成で、はい。素晴らしいなというふうに思いますんで、やっていっていただきたいと思います。
課長おっしゃられたんで、私もいおうと思ってたんですけど、無形のものに対して寄付をしてくれる方を私も知ってるんですけども、動物愛護であったり、動物保護に寄付を100万円、2件している人を私は知ってるんですけども高額所得者になるとものも持ってるからそんなにいらないんだって言う方もいるですね。
少ない金額だと何度も選ばないといけないので、僕にとっては少ない金額では全然ないんですけど、そういった層の方々に取ってやはりその興味があるプロジェクトであったりとか、活動にとか理念、ここ志に支援をしたいということで寄付をしているとなので、無形のものに対して例えば10万50万100万といった高額なものもメニューとしてあってもいいかなというふうに思います。
2024年のふるさと納税アワードのブロンズにも南木曽町は選ばれてますし、先ほども言いましたがもっとPRできれば、寄附金額も増加していくと考えられますので、こちらも意見としてよろしくお願いしたいと思います。
質問は以上で終わりたいと思います。
山下議員ご苦労さまでした。