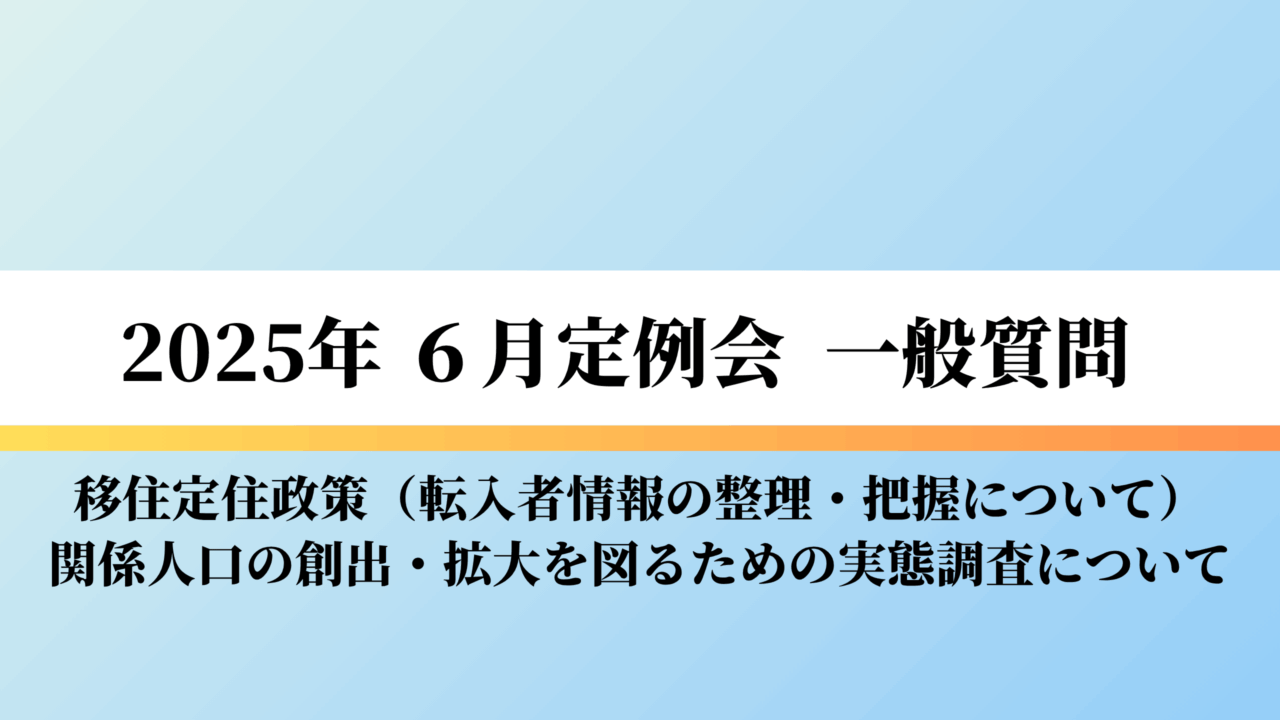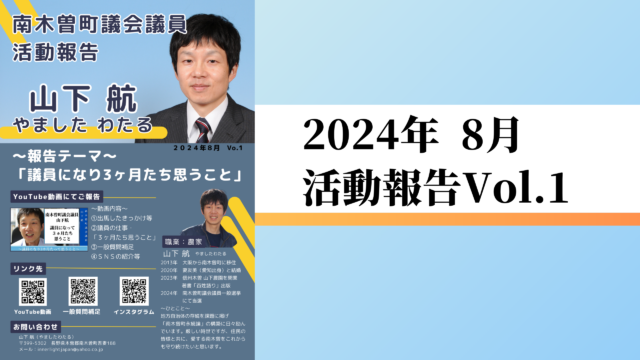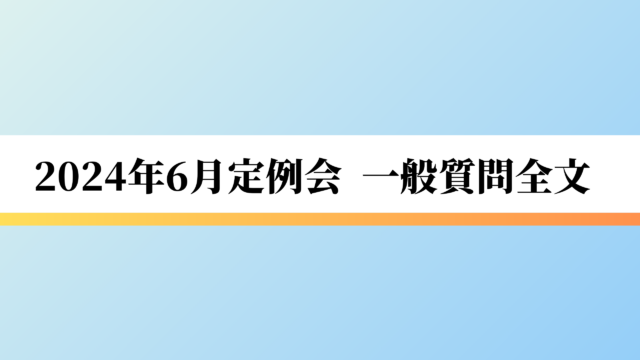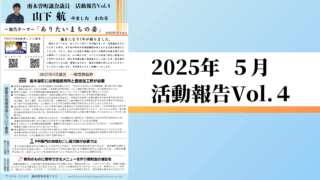一番山下です。
通告に基づいて一般質問を行いたいと思います。
私は移住定住政策、転入者情報の整理把握について、関係人口の創出拡大を図るための実態調査について質問します。
詳細につきましては自席で行いたいと思います。
一番山崎山下議員はい。一番山下ですよろしくお願いいたします。
移住定住政策転入者情報の整理把握について町外からの転入者は実際には就業や結婚介護事業、地域おこし協力隊等、目的や移住の経緯は様々ですそして、移住定住政策の成果効果を図るためにも、またPDCAサイクルを回し、政策の質を高めるためにも、転入者がどういった経緯で移住されたかを把握していることは必要です。
そこで伺います。
現在転入者情報などはどのような形で把握整理されているのでしょうか?特に毎年のUIターン者数は把握できているのでしょうか?
町長:移住定住政策につきましては、町のできている成果を検証しながら、より実効性のある事業として、でもありません。
近年では長野県が移住した意見No.1となっていたり、木曽町でも移住者が増加しているといった、身近に良いお手本がありますので、あの事例を参考にしてやはり移住者の声を聞いたりしながら、今後とも事業の展開を図っていきたいものと考えているところでございます。
ご質問の具体的な詳細につきましては、もっと元気に戦略室長からお答えをさせていただきます。
はい戦略室長はい。
戦略室長です。
現在の転入者情報などはの把握、整理の仕方ということでございます。
現在転入者の中には、先ほど議員おっしゃられたようにいろんな要因で転入されます。就業や家族の都合などいろんな失業、理由で転入されており全ての転入者の方の目的といったものを把握しているということではございません。
現在はその中でも現在は移住相談や空き家バンクの利用など、事前に接点のある方についてはこちらの方も移住他社としてカウントしております。
明確な点、定住を目的とした転入者まで把握てきていないというのが現状でございます。
また町が今把握しているというような形で、うちの方で事前に設定のある方として転入した方ということであれば、令和元年度からでいいますと、令和元年度で3万3名令和2年度で2名、令和3年度で2名令和4年度で6名、5年度で6名、6年度で6名、計25名というような形で把握はしております。
一番山下議員、一番です。ありがとうございます。
一部は、把握できているという状況だとは思います。
先ほど町長も言われましたけれども、以前木曽町の方で、移住者が増えてきているというふうに私も聞きまして、やっぱりそこで思ったのがい移住者というのは一体誰のことを指しているのかということでした。
私自身もこのことについて明確に理解できていなかったことに気づいて反省しましてそこで、各自治体がこのことについてどう把握しているのか。
またこの南木曽町ではどうなのかということで職員さんにも相談しました。
移住者数を調べることはできますかと尋ねたんですけども、この問いにですねやっぱりどういった伊集者数を調べればというふうにやっぱり迷ってしまったので、やっぱりこのことについては整理していかないといけないのかではいけないと思いまして質問をしました。
そこで資料の1配りしました資料の1を見ていただきたいんですけども、移住者とは具体的に誰のことということで、これは長野県のホームページより切り抜き、切り抜いた画像なんですけども令和6年度の移住者数が過去最多だったということですがこのページに移住者の定義と集計方法が載っていました。
この長野県の移住者の定義ということで、
全国統一の移住者の定義がないため、長野県独自に県外から新たな生活の場所を求め、自らの意思により店内に県内に転入したものとして集計集計方法としてはこの移住者アンケートおよび行政サポートによって補足した数とあります。
この移住定住政策と各自治体で打ち出していますが、実態としましてはこの移住者の定義がないまま、進んでいる政策でそういったものがまだまだ多いのかなというふうに思います。
そんな中で、独自に住所の定義をしている自治体もあり、この四角に囲んだ中に少し抜粋させていただきましたけども、こういったことを研究されている伊藤雅人さんっていう方によると、やはり独自に定義している。自治体の担当者は政策の効果は大きいと認識している傾向があると。
さらにこの転入者数というのは、出入りの数であるのに対して、移住者の定義には自治体それぞれの地域課題や目指す方向性が反映されてくる。
だからこそ自治体によって定義が異なってくる。
どんな人の維持を支援したいのか、どんな人に地域に来て欲しいのかつまり移住者の定義を考えるということが、この移住定住政策にとって非常に重要な部分であり、移住者定義を考える上では、転入者からの情報収集やヒアリングが必要になってくるのではということで、これ次の質問に行きたいんですけども、この南木曽町では現在の転入の手続き時点で、どの程度の情報を収集しているのでしょうか?
例えばどういった経緯で転入されるのか等の聞き取りは行っているのでしょうか?はい戦略室長はい。
戦略資料です。
転入手続きの際は水道やケーブルテレビその他各種新生活に関わる部分の手続きが多く、現在現住民の負担も多いため、移住の経緯など詳細な聞き取り等は実施していない状況にございます。
また長野県が実施する転出転入アンケートの案内は行っていますが、QRコードによる任意の回答方式でのため、間回答率については極めて低いというような状況となっています。
また転入時の手続きで、町が取得できる情報については、お名前、住所、生年月日家族構成などといった、ことに限られております。
職業や移住の理由などの情報については個人情報の保護の観点もあり、今の現在収集はしていないというような状況でございます。
一番山下議員、一番山下です。
質問の前にちょっと一つお伝えしたいんですが私が転入するときは、地方創生と言われだしたときで、地域おこし協力隊の制度もないときで、まだその窓口での移住者対応の取り組みなどもなかったように思います。
独自の職員の人にとってもある日突然現れた大阪からの転入者だったというふうに思います。
そのときの窓口での対応というのは今でも印象に残ってるんですけども、やはりちょっと心遣いをがあったなというふうに思いますゴミの出し方とか大丈夫ですかとかそういった声をかけてくれたので、あれは本当に非常に嬉しかったですし、その声かけ一つで移住してよかったなというふうに思えるものでした。
そういった今の窓口の対応も気になるところではありますが今回はそこがロンドン論点ではないので、質問は視認しませんが切り分けていただけたらなというふうに思います。
先ほど県からのアンケートがあるというふうにお聞きしましたが、
やっぱりそういったアンケートを取るという方法で、個人情報の方、個人情報の方も保護しながら、やっぱり町独自としてのアンケートを取るといった方法がいいのではないかなというふうに思うのでその情報収集の仕方と、転入手続き地点で取り入れ取り入れることについて、検討していただけないでしょうかどうでしょうか?戦略室長転入者の経緯や背景を把握することについては、移住定住政策の効果検証や改善に非常に重要だと考えられます。
今後の対応としましては、
住民の窓口担当と相談しながら、転入手続きの際に選択式を中心とした設問での窓口負担を最小限にふ加え抑えるような形で工夫した形でアンケート調査が実施できるものかどうかということを検討はしていきたいと思います。
一番山下議員はい。
一番山下です。
おっしゃったように役場の業務負担を最小限に抑えつつ移住政策の成果を見極めるためにも、戦略室住民課なのかわかりませんがその課を横断して、うまくそのあたりは連携していただけたらなというふうに思います。
この質問は以上になります。
次の質問に行きたいと思います。
関係人口の創出拡大を図るための実態調査について総務省では関係人口の定義として、地域と多様に関わる人々で定住しないが、地域と持続的に関わりを持つ人としています。
そして南木曽町では交流活動の推進からこの関係人口を増やして、中定住に繋げていこうという、総合計画の方針も見受けられます。
そこで伺います。
まず、南木曽町における関係人口の定義について教えてください。
はい戦略室長はい。
戦略室長です。
関係人口、今、議員おっしゃるように総務省の定義によりますと、移住した定住
人口でもなく、観光に来た交流人口でもない地域やや地域の人々と多様に関わる人々というような形で示されております。
地方では人口減少高齢化により地域作りの担い手不足という課題に直面しています。
その中でも地域によっては若者を中心に、地域外の人材が地域作りの担い手となる。
変化を生み出す人材として、地域に入り込み始めています。
そういった関係人口と呼ばれるボランティア活動や副業、2地域居住などをしているそうでございます。
これを参考にしますと、南木曽町においては、南木曽町には定住はしていないものの町内
の人や地域資源自然や文化に継続的に関わり、南木曽町と関係性を築いている人々となるものと考えられます。
具体的に言いますと、いかなこれから申し上げるような方を想定しています。
過去の居住や勤務などで、南木曽町に関わりがあり、思い入れのある方町内に親戚や友人がいて、頻繁に訪れてくれる方大学連携事業などを通じて、地域課題を解決などに取り組む方々地域行事や体験イベント等に継続的に参加する方また来庁しないでもふるさと納税等で継続的に
木曽町を支援していただいていただける方また新たに整備されました。
永住体験住宅等の利用者や空き家大金ツアーなど、移住を検討している方々などが観光人関係人口として想定される方々と考えております。
はい。
一番山下議員、一番山下です。
定義についてですが共有できて良かったと思います。
総務省であったり国土交通省もこの関係人口の経費について述べてます。
中身が少し違っていって、学術者の間での定義がまちまちで、逆に関係人口の場合は明確に定義しない方が良いのではないかと
おっしゃっている方もおられます。
デジタル関係人口という言葉も生まれてきたりですねこの対応で変化の多いものなので、現在おっしゃっていただいた定義さらに今後どういうふうな形にしていくのかというふうに変わる可能性もあるかとは思うんで、その課題として挙げておく必要があるかなと思いまして質問いたしました。
ここでは定義についてさらにということは今回は意図していないのでどういった人たちがこの南木曽町と関係を持っているのか。
その傾向を知ることが重要ではないかというふうに思いますので、次の質問にいきたいと思います。
関係人口の創出拡大を図るにあたり、
実態の把握、つまり交流事業やイベント等を行った後に、関係人口がどのくらい創出されたのか。
かなどの調査は現在、どのような体制方向で方法で行われているのでしょうか仮に現時点で十分な調査が行われていない場合は、今後どのような形で記録分析を行い可視化していく計画でしょうか?はい戦略室長はい。
戦略書です。
現時点において関係人口の創出につきましては、大学連携事業や、大同特殊鋼等の森林里親事業上下流交流、長久手市との交流など今後
系人口に繋がっていくんではないかという取り組みを行っているところでございます。
いずれにおきましても、その後の進捗把握等については現在のところ行っていないという状況にございます。
また今後どのように把握していくか研究していきたいとは思いますが、当面は移住体験施設の利用者や地域おこし協力隊が造成する体験ツアーの活動を通じて、南木曽町と接点を持つ関係人口の方々と連絡を取り合いながら、実態把握を進めていきたいと思います。
また国では、関係人口をの可視化する取り組みとして、ふるさと住民登録制度の創設を検討しているというような情報を聞いています。
住所地以外の地域に継続的に関わる方々を、誰もがアプリで簡単に鑑別簡便に登録できるふるさと住民登録という仕組みを考えているようです。
詳細はまだわかりませんが、2地域居住や地域ボランティア、副業、観光でのリピーターや繰り返しのふるさと納税などを通じ、地域経済や地域の担い手として活用。
活躍される方が自治体ふるさと住民として登録し、ふるさと住民として貢献することで、自治体からの情報提供や行政サービスの提供が受けられるというような制度のようでございます。
こういった形で関係人口の登録制度ができれば、いろんな形で関わり方の情報を
収集する収集や分析評価などできると思いますので、可視化に繋がるのではないかと考えております。
一番山下議員はい。
一番山下です。
今後行っていくという方向性ということでわかりました。
やはりできる範囲でまず始めていってほしいなというふうに思います。
やっぱり南木曽町等の継続的に関わりのある方はたくさんおられると思いますし、行動実態を把握していくのかを決めていく必要があるとは思います。
資料の②なんですけども、こちらは参考程度にはなりますが、国土交通省の調査でもやはり関係人口の増加は、永住者増加に効果があると認めています。
私も元々関係人口ですから
実感があります。
やっぱり人が急に明日受賞なんて絶対にならないわけで、やっぱり必ず関係人口という地域との何らかの関わりを持とうとします。
過去にはマラソン大会に出て行って移住された方もいますし、私なんか商工会さんの主催だったと思うんですけどもスローフードフェスタにも参加してましたし、住民の方がされていた農園のイベントに参加して地域おこし協力隊になった方もおられます。
この関係人口の拡大と創出を大きくしていくためにやはりその定量的な定性的な関係人口のデータの可視化が前提になってくるかなというふうに思いますので今後整備していってほしいなというふうに
思います。
最後になんですけども、この移住定住、関係人口の創出拡大の政策においてお伝えしたいことなんですけども今年の3月に、移住者交流会を町の方が開催してくれました本当にイベントは良かったと思います。
あと参加者の方々と個人的に繋がりまして、4月5月と口コミで移住者交流会を行いました。
3回目も要望があって7月ぐらいに予定をしているところですそしてそこには20代前半の方から、50代の方まで参加し基礎にこの移住を検討しているという方も参加されました。
これは私はこの町の政策で起こった地域活性化だと思っていて、この結果
今日作ったのは職員さんたちです。
利用させていただいて、利用させていただいたこのお店の売り上げも上がっているわけで、これは行政の成果として評価されるものだと思っています。
そして今回イベント後にこういったことが起きてますよということで職員さんにお伝えできたからよかったんですが、こういったイベント後に事後の調査が行われてなかったですねこういうことが町で起きているということがわからないままになってしまいます。
せっかくその成果が出ていても、行政の評価に繋がらないのはこの正しい評価にならないのではないかなというふうに思っています。
この事後調査をせずに効果がないと判断してしまって政策をやめてももったいない結果になります。
やっぱり成果っていうのは伝わって初めてこの評価の対象になるものなので、
丁寧に調査押していただいて、政策の効果について自分たちで改めて知り、適切な評価を受けていただきたいなというふうにそんな思いであります。
最後に一つ質問させていただきたいんですけどもぜひともこういったイベントに、今言った、起きたこと、こういったことも成果報告書に上げていただけたらなというふうに思うんですけどもいかがでしょうか?戦略室長はい。
またちょっとそ作成時に、考えていきたいと思います。
一番山下議員一番山下です。
ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
以上です。